森川すいめい先生の勉強会に行き、しっかり考える時間を頂きました。
と同時に、考え過ぎてはいけない事もあるかもと思いました。
例えば、患者さんの相談を受け、その方の辛さに寄り添おうと思いを馳せたとしても、そこには自分の経験が混ざります。どんなに考えても患者さんの思いとはピタリとは合致しません。
似たような体験をしていれば、より共感の気持ちは強くなりますが、その人と自分は他者であるということを大切にしなければなりません。似ていても同じでは無い。どんなに思いを馳せてもその人ではないからホントの辛さの程度はわからないんですよね。意外とそれほどでもないかもしれないわけです。
解決しようとしたり評価しようとしたり。寄り添って共感し、この人は〇〇だから△△の支援が必要に違いないと決めつけてしまったり。
相手に寄り添おうとする姿勢は必要でも、必ずそこに「他者性」があることを持っていないと、とんでもない勘違いが起こってしまうこともある。
今まで、寄り添うことを大切に考えてきたけど、他者性を大切にした上での寄り添いは、自分自身も大切にする寄り添い方だなと思いました。
私は寄り添おうとする時に、その人と同じになろうとしてましたが、その人の横、または後ろに立ち、その人が見ているものを見るイメージ!同じものを見ていても、相手には相手の、私には私の歴史がある。
以前、仕事の上で寄り添いすぎて辛くなることがあったけど、それはその子と自分を同じ器の中に入れて感じてしまったから。「他者性」を持った上で寄り添う。となると、その人の見た景色、経験したことを、そのまま捉えてそこに自分の感情や思考を混ぜない。考えすぎてはいけない。決めつけてはいけない。
「他者性」忘れっぽいけど、忘れたくない感覚を得られました。


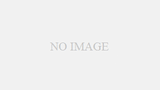
コメント